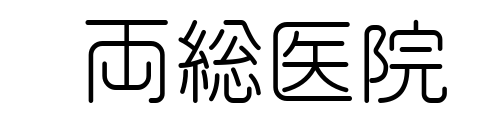治療方法におけるECTの立ち位置
1. 効果が期待できる治療
ECTは、主にうつ病・双極性障害・統合失調症・緊張病などに対して行われます。特に次のような状況で効果が期待されています。
うつ病・双極性障害のうつ状態
- 薬の効果が十分でないとき
- 強い気分の落ち込みや、自殺を考えてしまうほどつらいとき
- 妄想を伴う重症のうつ病
- 食事や睡眠がとれず、体調が大きく崩れているとき
双極性障害の躁状態
- 重度の興奮状態や攻撃性があり、薬物療法だけでは改善が難しいとき
- 緊急に症状を落ち着かせる必要があるとき
統合失調症
- 薬を使っても症状がなかなか良くならないとき
- 急性期で症状が非常に重いとき
緊張病(カタトニア)
- 動かない、話さない、食事や水分が取れないなどの症状があるとき
- ECTは緊張病に対して特に高い効果を示し、生命の危険がある場合の重要な治療選択肢です
ECTの効果の特徴
- 即効性: 数回の治療(1-2週間程度)で効果が現れることがあり、薬物療法(数週間)よりも早く改善が見られる場合があります
- 高い反応率: 薬剤抵抗性うつ病に対して50-70%程度の反応率が報告されており、複数の薬を試して効果がなかった場合と比較して高い効果が期待できます
2. 他の治療との違い
薬物療法との違い
- 効果が出るまでの時間: 抗うつ薬や抗精神病薬は効果が出るまで数週間かかることがありますが、ECTは比較的短期間で改善が見られることがあります
- 作用機序: 薬物療法は神経伝達物質に働きかけますが、ECTは脳に電気刺激を与えることで、より広範囲に神経回路や神経伝達物質の働きに変化をもたらします
- 緊急性への対応: 希死念慮が強い、食事が取れないなど、緊急に症状を改善する必要がある場合、ECTの即効性が重要な選択理由になります
心理療法との違い
- アプローチ: 心理療法は考え方や生活習慣に働きかける治療ですが、ECTは脳に直接働きかけて神経回路の機能を改善する治療です
- 適用場面: 心理療法は症状がある程度安定している状態で効果を発揮しますが、ECTは重症で心理療法が困難な状態でも実施できます
- 組み合わせ: 対立するものではなく、ECTで症状を改善した後、心理療法で再発予防を図るなど、補完的に使用されます
安全性の特徴
- 幅広い患者さんに対応可能: 高齢者や妊娠中の方、身体疾患を持つ方にも比較的安全に実施できます
- 薬物療法が使いにくい場合の選択肢: 薬の副作用が強い方や、薬物相互作用が懸念される場合にも選択肢となります
- 現代の安全性: 全身麻酔下で行われる修正型ECTは、麻酔を伴う他の医療処置と同等の安全性があり、重篤な副作用は稀です
3. 薬物治療との組み合わせ
ECTは単独で行われることもありますが、多くの場合、他の治療と組み合わせて総合的な治療計画の中で実施されます。
- 急性期: ECT実施中も必要に応じて薬物療法を併用します
- 維持期: ECTで症状が改善した後、再発を防ぐために薬物療法を継続することが一般的です
- 維持ECT: 場合によっては、症状が安定した後も定期的にECTを継続する「維持ECT」が行われることもあります。これは薬物療法と併用されることが多いです
このように、ECTは他の治療法と対立するものではなく、それぞれの治療法の長所を活かした総合的な治療の一部として位置づけられます。
4. ECTの位置づけ
国際的な評価
世界の精神医学会のガイドラインでは、ECTは以下のように位置づけられています。
- 薬剤抵抗性の重症うつ病に対する有効な治療法
- 双極性障害のうつ状態および躁状態に対する治療選択肢
- 統合失調症の急性期や薬剤抵抗性の場合の治療法
- 緊張病に対する第一選択の治療法
日本での位置づけ
- 日本の精神科医療においても、安全で効果の期待できる治療の一つとして確立されています
- 大学病院や総合病院の精神科を中心に実施されており、近年では日帰りECTを提供する施設も増えています
治療選択のタイミング
- 「最後の手段」ではありません: 従来は複数の薬を試した後に検討されることが多かったですが、現在では症状の重症度や緊急性によって早期に検討されることもあります
- 緊急性が高い場合: 強い希死念慮がある、食事や水分が取れない、緊張病で生命の危険があるなど、緊急に症状を改善する必要がある場合には、早い段階でECTが選択されることがあります
注意点
患者様のご希望だけでECTは行いません
以下のような条件にあてはまる場合で、医師が必要と判断した場合にのみ、ECTを施行します
- 迅速で確実な臨床症状の改善が必要とされる場合(自殺の危険、拒食・低栄養・脱水などによる身体衰弱、昏迷、錯乱、興奮、焦燥を伴う重症精神病など)
- 他の治療法の危険性がECTの危険性よりも高いと判断される場合(高齢者、妊娠、身体合併症など)
- 以前の1回以上のエピソードで、薬物療法の反応が不良であったか、ECTの反応が良好であった場合
- 薬物の選択、用量、投与期間、アドヒアランスの問題を考慮した上で、薬物療法に対する抵抗性が認められる場合
- 薬物療法に対する忍容性が低いか副作用が認められ、ECTの方が副作用が少ないと考えられる場合
- 薬物療法中に精神状態または身体状態の悪化が認められ、迅速かつ確実な治療反応が必要とされる場合